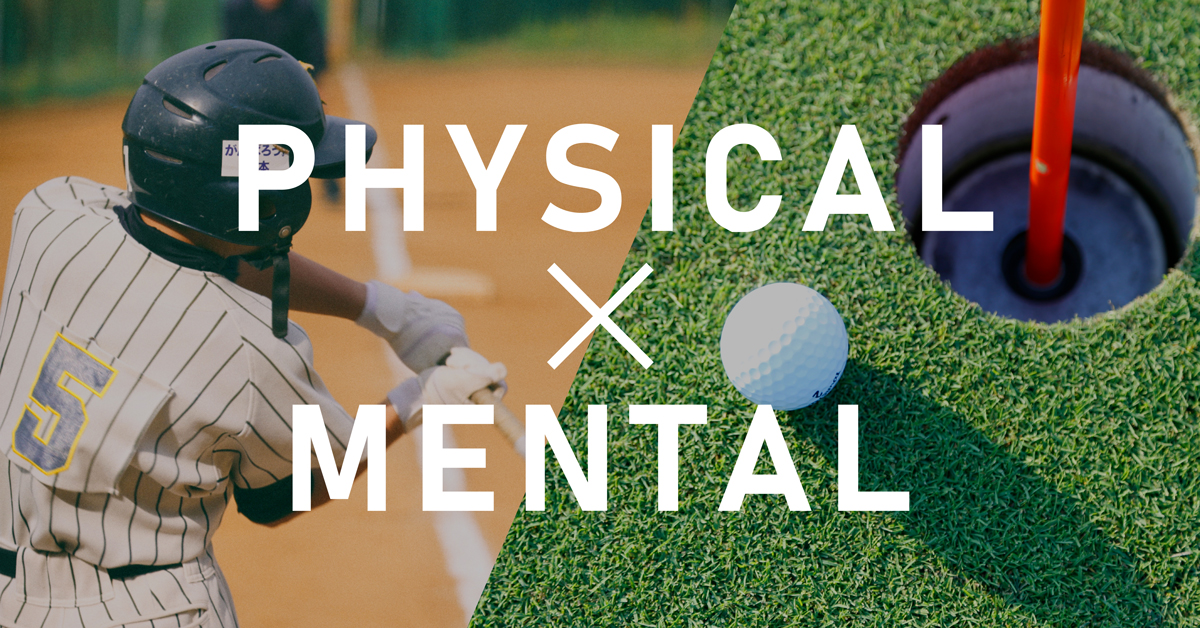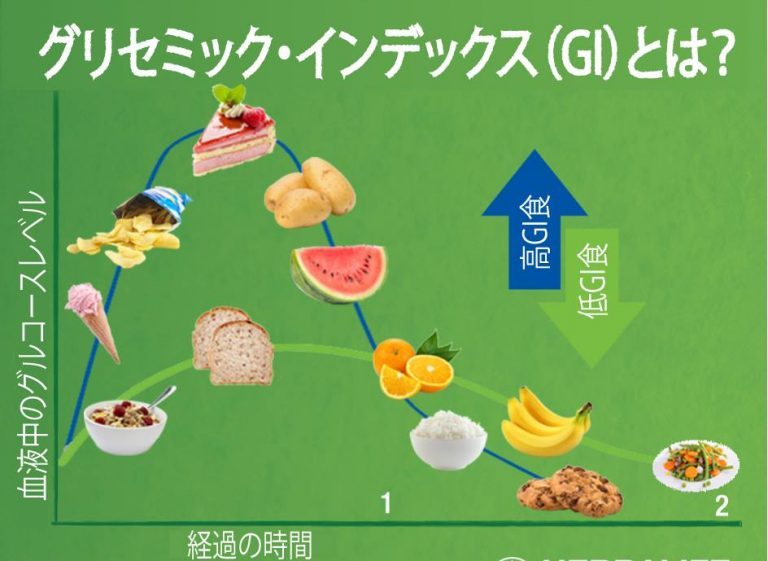-
- 2022/02/17
- トレーニングブログ
ビジョントレーニングって何?
今更聞けない、ビジョントレーニングの重要性。
 こんなトレーニングだけやってビジョントレーニングだー!!といっているのは危ない
こんなトレーニングだけやってビジョントレーニングだー!!といっているのは危ない
ビジョントレーニングって言葉は本気でパフォーマンスを上げたくて、本気でスポーツを取り組んでいる学生なら聞いたことがあるだろう。
ビジョントレーニングをやっているそのスポーツのトップ選手も多くなってきているし、
ビジョントレーニングを取り入れるトレーナーも増えてきている。
ビジョントレーニングはメンタルトレーニングにもなりうるのだ。
なぜ眼のトレーニングがメンタルトレーニングになるのかは、機能神経学を学んでいる治療家やトレーナーならすぐに答えられるはず。
逆に言うと、メンタルトレーニングコーチとうたっているにもかかわらず、眼の重要性を理解していないとするならエセ野郎だといっても差し支えないだろう。
 こんなトレーニングだけやってビジョントレーニングだー!!といっているのは危ない
こんなトレーニングだけやってビジョントレーニングだー!!といっているのは危ないという前置きはこの辺にしておきまして、本日の内容は、永井の自己満投稿を見ていただければ幸いです。
永井は、他のトレーナーが考えている事より、かなり深いところまで学び考えております。
人間はなぜ、今の構造になったのか? パフォーマンスをアップさせるに、つまるところこの問を追求する事が大事です。
この問いを追求するにあたり、避けては通れないのは、進化論です。 魚類から両性類となり爬虫類や鳥類その果てに哺乳類となっていくわけですが、
この比較をしていく事で人間が人間であるためにやるべき事が見えてくるわけです。
昨今、トレーナーや施術家を名乗る人が増えているし、いろいろな事が学べる環境がある。
しかし、どのメソッドや教育も個体差を根本として考えていないで、二元論や型にはめて考えている。
眼の働きを一つ考えてみよう。
本来 眼は視る事が役割!!ではなく、探索するためにあるのだ!!!!
面白いことにクジラは海→陸→海というように住み生活の場所を変えていった哺乳類なのだ。
クジラの骨の構造には頸椎(首の骨)がない。
私が考えつく理由として2つ
・水中では視覚は聞かないので要求度は低くなり、触覚や聴覚への要求度が増す。
・水圧に対して体が負けないようにする適応として。
この事により、頸椎を退化させる事で水の中での移動として効率な進化を遂げたのだ。
翻って人間の個体差に目を向けると、柔道やレスリング、相撲といったスポーツは頸部が太く短い。
バスケやバレーボールは長く細いと相対的に言っていいと思う。 これは、中学生や小学生の時には見られない傾向だと思うが、
高校、大学、プロとなるにつれその傾向は顕著になる。
筋肉のつき方はそのスポーツを行う事で必要なものが必要なだけついていく適応を遂げるが、
適応して結果としてではない側面もあると思うのだ。。。
小学生の時に水泳がどうにも苦手・球技がどうも苦手。という個性がみられると思うが、この個性はその後子供がどのようなスポーツが
得意になるかのいい材料となるんではないだろうか?と私は思うのだ。
違う見方をすれば、その人の弱点というのも浮き彫りとなり、パフォーマンスを上げるためにより効率のいいトレーニングを
構築する指標ともなる。
長い人生においてはスポーツをやめてからの人生において体の不調(肩こり、腰痛など)にもかなり影響しそうだ。
患者様が来た時に、主訴を聞くだけでなくその人の人生のストーリーにも焦点を当ていろいろな事を聞く事でその人に必要な
アプローチが見えてくる。
読んでいただいた方の中には、結局あんたも型にはめているよね。と思う方もいるだろうが、
型を人間だけをとってつけた型なのか、どこまで掘り下げていった結果の型なのかによってだいぶ違うと私は思うのだ。
話を学生スポーツにもどせば、バスケをやっている子は比較的細く、日本離れした体形の子が多い。
そんなモデル体型の子はやはり頸部の筋肉や胸郭の強度を増すようなトレーニングが絶対必要だが、そこに偏った結果
持って生まれた素質である軽やかさや柔軟な動きを失わせてはいけない。
違うタイプでいえば、バスケをやっています!!でもちょっとぽっちゃり体形の子というのも昨今は珍しくない。
そんな子は、体幹トレーニングに始まる筋トレに特化するより、もっと必要な事がある。
その一つにビジョントレーニングもはいってくるんだろう。
そんな事を考えて日々学生スポーツに励む皆さんとのトレーニングを行っている。
![]()
NEW RECCOMEND ARTICLE オススメ記事新着
![]()
PICKUP ARTICLE よく一緒に見られている記事
- CATEGORYカテゴリー
- すべて
- リベロスタッフブログ
- トレーニングブログ
- 体のお悩みブログ
- 子供の悩みブログ
- ARCHIVEアーカイブ